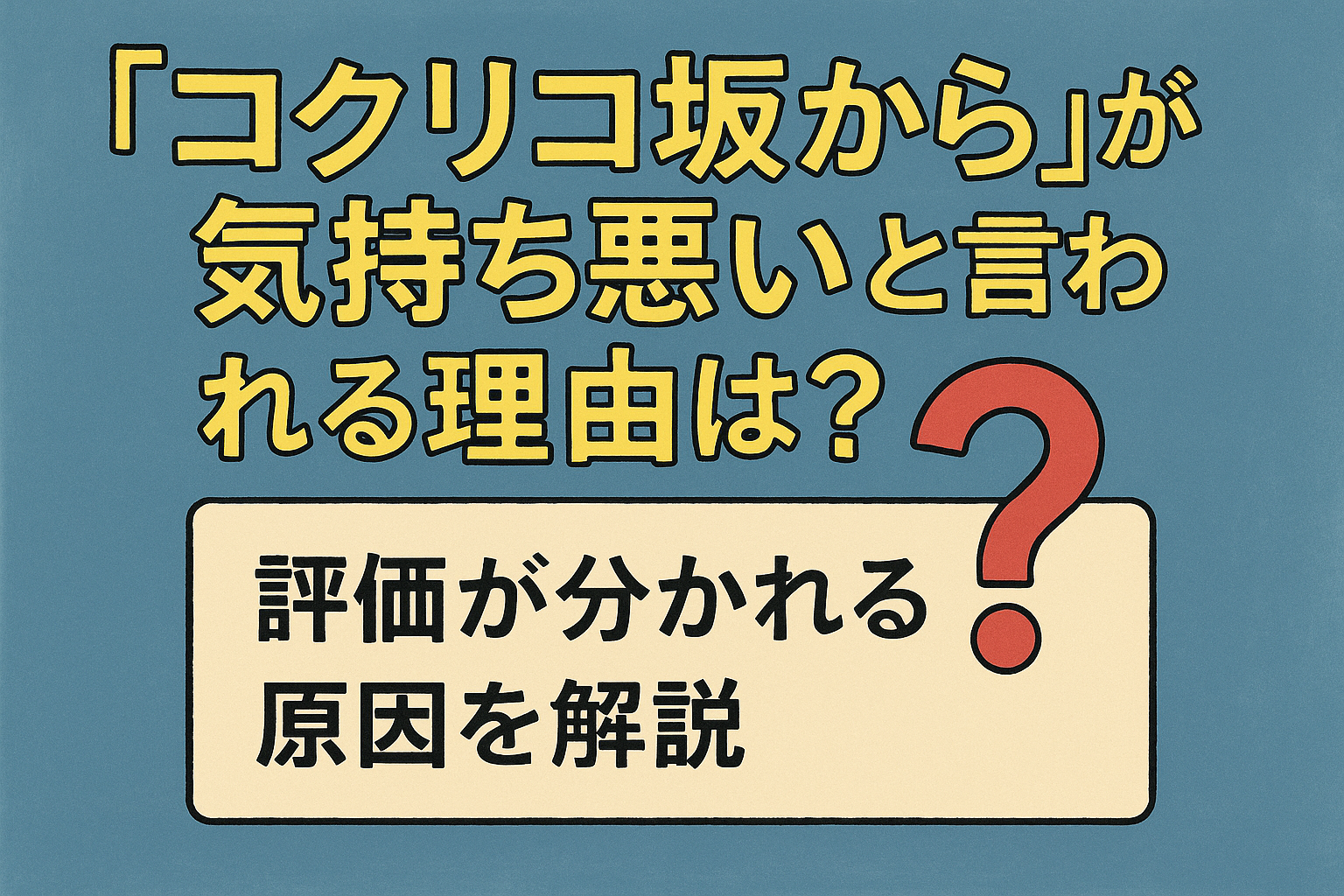レコードくん
レコードくん『コクリコ坂から』を観た後のモヤモヤ、気持ち悪いと感じる理由は何?
スタジオジブリの映画『コクリコ坂から』を観て、「なんだかスッキリしない」「登場人物の行動がよく分からない」と感じていませんか。爽やかな青春物語のはずなのに、一部で「気持ち悪い」という感想があがるのは、はっきりとした理由があります。
そのモヤモヤとした気持ちの正体を知らないと、作品が持つ本来の魅力を見逃してしまうかもしれません。この記事では、『コクリコ坂から』が「気持ち悪い」と言われてしまう9つの理由を、視聴者の感想を交えながら分かりやすく解説していきます。この記事を読み終える頃には、あなたが感じた違和感の正体が明らかになり、作品への理解がより一層深まることでしょう。
コクリコ坂からが気持ち悪いと言われる理由


『コクリコ坂から』が一部の視聴者から「気持ち悪い」と評価されるのには、いくつかの理由が挙げられます。近親相姦を思わせる恋愛描写や、複雑で説明不足なストーリー展開が、観る人に違和感や不快感を与えてしまうようです。ここでは、そうした評価に繋がった具体的な要因を一つひとつ掘り下げていきます。
兄妹かもしれない二人の恋愛描写が気持ち悪い
この作品が「気持ち悪い」と言われる最も大きな原因は、主人公の海と風間俊が兄妹かもしれないという状況で恋愛関係が進んでいく点にあります。物語の途中で、二人は同じ父親を持つ可能性があると知りますが、それでもお互いへの気持ちを止められません。
特に、「たとえ兄妹でも好き」と互いの気持ちを確かめ合うシーンは、近親相姦を連想させ、生理的な嫌悪感を抱く視聴者が少なくありません。 ジブリ作品の持つクリーンなイメージとはかけ離れた禁断の恋というテーマが、多くの人に衝撃と不快感を与えてしまったのです。最終的に血の繋がりはないと分かりますが、それまでの過程が気持ち悪いという感想に繋がっています。
実際には兄妹でない設定への混乱
物語の終盤で、海と俊には血の繋がりがないことが明らかになりますが、この展開が視聴者の混乱を招いています。 物語の大半は「二人は兄妹かもしれない」という重い葛藤の中で進んでいきます。 この設定が、二人の恋愛を純粋な目で見られなくさせ、視聴者に大きなストレスを与えてしまうのです。
そして最後に「実は兄妹ではありませんでした」という結末を迎えるため、それまでの悩みや葛藤が一体何だったのかと、展開が唐突でご都合主義に感じてしまう人もいます。 どんでん返しを狙った設定が、かえって物語への没入を妨げ、後味の悪さを残す結果になっているようです。
ストーリーがつまらなくて面白くないという感想
『コクリコ坂から』は、他の多くのジブリ作品と比べて、ファンタジー要素や派手なアクションシーンがありません。物語の中心は、高校生の男女の淡い恋愛と、古い部室棟「カルチェラタン」の保存運動という、非常に現実的で静かなテーマです。
そのため、ワクワクするような冒険活劇を期待して観た人からは、「ストーリーが単調でつまらない」「退屈だった」という厳しい意見が出ることがあります。 何を伝えたいのかが分かりにくいという感想もあり、物語の核となる青春群像劇としての魅力が伝わりづらい点も、面白くないと感じる一因かもしれません。
家族一緒に見るのが気まずい内容
本作の核心に触れる「兄妹かもしれない二人の恋愛」というテーマは、家族で一緒に観るには少々気まずい内容です。リビングで親子が並んで観ている時に、近親関係を匂わせるシーンが流れると、気まずい空気が流れてしまうことは想像に難くありません。
特に、小さな子供に「どうしてこの二人は悩んでいるの?」と聞かれた際に、どう説明すれば良いのか戸惑う親も多いでしょう。ジブリ映画だからと安心して家族で観始めたものの、予期せぬ重いテーマに戸惑い、気まずさを感じてしまうケースがあるようです。
突然歌い出すシーンが違和感を与える
物語の途中で、登場人物たちが突然合唱を始めるミュージカルのようなシーンがあり、これに違和感を覚えるという声も少なくありません。例えば、部室棟の存続をめぐる討論会が白熱した場面で、学生たちが「白い花の咲く頃」を歌い出すシーンがあります。
これは1960年代に流行した「歌声喫茶」のような文化を反映した演出ですが、現代の感覚からすると唐突に感じられ、物語の流れを止めてしまうと感じる人もいるようです。ジブリ作品としては珍しいこの演出が、一部の視聴者には馴染まず、違和感として受け取られてしまいました。
時代背景が難しく理解できない
物語の舞台は、東京オリンピックの前年にあたる1963年(昭和38年)の横浜です。 この時代は高度経済成長期の真っ只中で、古いものが壊され新しいものが次々と生まれていく活気に満ちていました。 一方で、戦争の傷跡もまだ生々しく残っており、海の父親である澤村雄一郎は朝鮮戦争で亡くなっています。 また、俊の出生の秘密には、原爆や戦後の混乱が深く関わっています。
本格的な学生運動が盛り上がるのはもう少し後ですが、その前夜ともいえる当時の空気感も含め、こうした時代背景を知らないと、登場人物たちの行動や価値観に共感しづらい部分があります。 歴史的な知識がないと物語の深い部分が理解できず、ただの古い話と感じてしまうかもしれません。
主人公の呼び名「メル」と名前「海」の関連性が不明
主人公の松崎海(まつざき うみ)は、家族や友人から「メル」という愛称で呼ばれていますが、なぜそう呼ばれるのか作中で明確な説明がありません。 この「メル」は、フランス語で「海」を意味する「la mer(ラ・メール)」に由来しています。
しかし、この事実を知らない多くの視聴者にとっては、「海」という名前と「メル」という呼び名が結びつかず、混乱の原因となっています。 ちょっとしたことですが、こうした説明不足な点が積み重なり、物語に入り込みにくくさせている一因と言えるでしょう。
主人公が家事を一人でしている理由が分からない
高校2年生の海が、下宿屋「コクリコ荘」の家事をたった一人で切り盛りしている姿に、疑問を感じる視聴者もいます。 母親は大学の研究者で留学中、父親は既に亡くなっているという設定ですが、同居している祖母や妹、さらには下宿人たちがなぜもっと協力しないのか、という点に違和感を覚えるのです。
責任感の強い海が一人で抱え込んでいるようにも見えますが、高校生にこれほどの重労働をさせている状況は、現代の価値観から見ると少し不自然に映るかもしれません。しかし、当時は家長が不在の家庭で長女が家事全般を担うことも珍しくなく、そうした時代背景を反映した設定ともいえます。
子供にはストーリーが複雑すぎる
『コクリコ坂から』は、恋愛、出生の秘密、学生たちの活動、戦争の記憶といった、大人の事情が複雑に絡み合う物語です。 そのため、ジブリ作品だからといって小さな子供が観ても、内容を十分に理解するのは難しいでしょう。
ファンタジーやアクションといった子供が喜ぶ要素も少ないため、多くの子供にとっては「退屈な映画」と映ってしまう可能性があります。大人向けの青春ドラマであり、ターゲット層がこれまでのジブリ作品とは少し異なるため、子供が楽しめずに終わってしまうことが多いようです。



「気持ち悪い」と感じる理由は一つではないんですね。特に、物語の核心である二人の関係性が、見る人によって大きな違和感を与えてしまうようです。
コクリコ坂からの魅力について
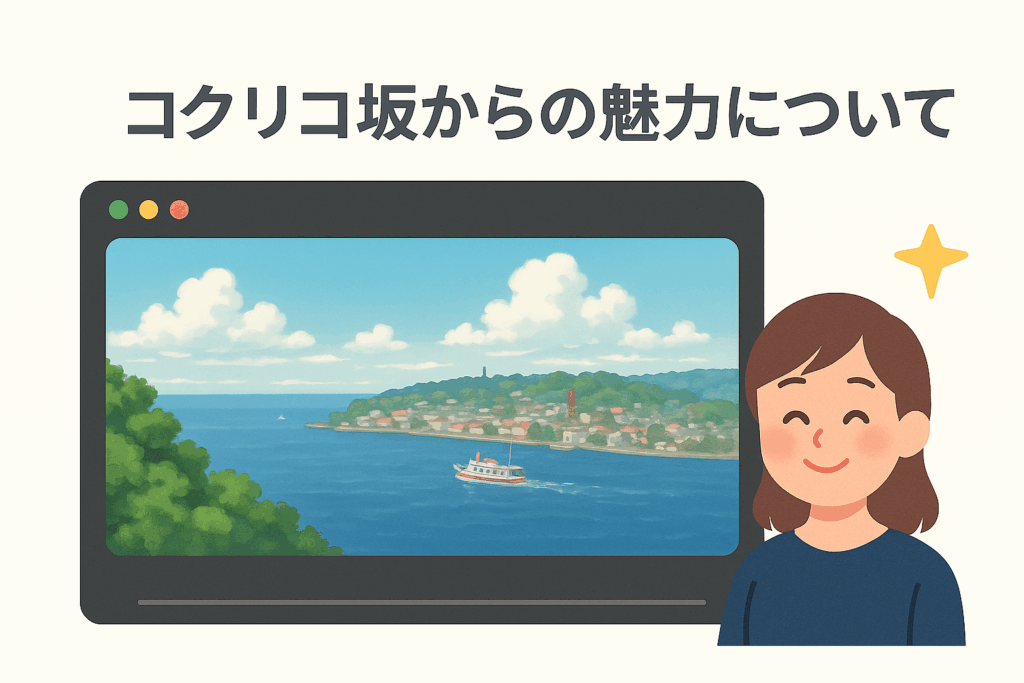
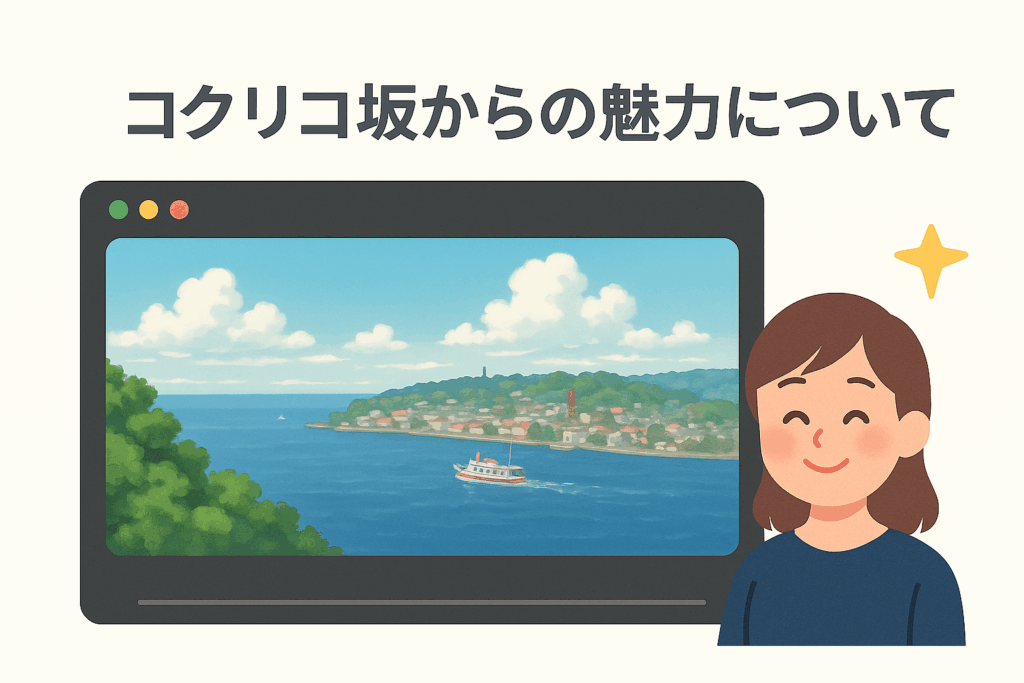
『コクリコ坂から』は、様々な意見がある一方で、多くのファンに愛されている作品でもあります。その魅力は、映画ならではの追加要素や、丁寧に描かれた時代背景、そしてジブリらしい細やかな表現に隠されています。ここでは、一部の批評的な意見とは異なる視点から、本作が持つ本来の魅力について深く掘り下げていきましょう。
原作にはないカルチェラタンが魅力的
映画の重要な舞台となる文化部棟「カルチェラタン」は、原作の漫画には登場しない映画オリジナルの設定です。 この建物は、様々な文化部が雑然と活動する学生たちのエネルギーの象徴として描かれています。哲学部、化学部、新聞部などがごちゃ混ぜになったカオスな空間は、古いけれど活気に満ちあふれており、見ているだけでワクワクさせられます。
このカルチェラタンの存続をかけて学生たちが一丸となる姿は、本作の大きな見どころの一つです。原作が主人公二人の恋愛模様を中心としているのに対し、映画はこのカルチェラタンという場所の魅力を加えることで、物語に深みと青春群像劇としての面白さを与えているのです。
昭和レトロな青春時代の雰囲気を楽しめる
本作の舞台である1963年(昭和38年)の横浜は、ノスタルジックな魅力にあふれています。 坂の多い街並み、活気ある商店街、走る路面電車など、当時の風景が丁寧に描かれており、まるでタイムスリップしたかのような感覚を味わえます。 学生たちの服装や髪型、坂本九の「上を向いて歩こう」といった流行歌など、昭和レトロな雰囲気が好きな人にはたまらない要素が満載です。
高度経済成長期の、古き良きものと新しいものが混在する独特の空気感の中で繰り広げられる青春物語は、当時を知る世代には懐かしく、知らない世代には新鮮に映ることでしょう。
ジブリならではの独特な世界観を味わえる
派手さはないものの、日常を丁寧に描くという点において、本作は非常にジブリらしい作品と言えます。特に、海が毎日作る朝食や、アジフライを揚げるシーンなど、ジブリ作品特有の美味しそうな食事の描写は健在です。
また、主題歌や挿入歌の使い方も印象的で、手嶌葵の透き通るような歌声が、作品の切なくも爽やかな雰囲気を一層引き立てています。一見地味に見える物語の中に、登場人物たちの心の機微や、時代の空気感を細やかに表現する。こうしたジブリならではの繊細な世界観が、本作の大きな魅力となっています。
あえてのメロドラマ風な演出が心地よい
一部の視聴者に強い印象を与えた「兄妹かもしれない」という設定ですが、これを昔ながらのメロドラマとして楽しむ見方もあります。俊自身が「まるで安いメロドラマだ」と自嘲するセリフがあるように、作り手側もこの展開を意図的に演出していると考えられます。
禁断の恋という大きな障害があるからこそ、二人の想いはより純粋に、切なく燃え上がります。こうした王道とも言える恋愛ドラマの展開が、かえって新鮮で心地よいと感じるファンも少なくありません。全編を流れるどこか懐かしい雰囲気と相まって、古き良き時代の恋愛映画を見ているかのような気分に浸ることができるのです。



批判的な意見もありますが、映画ならではの魅力もたくさん詰まっています。特に、原作にはない「カルチェラタン」の存在が、物語をより豊かにしているんですよ。
コクリコ坂からについてのよくある質問
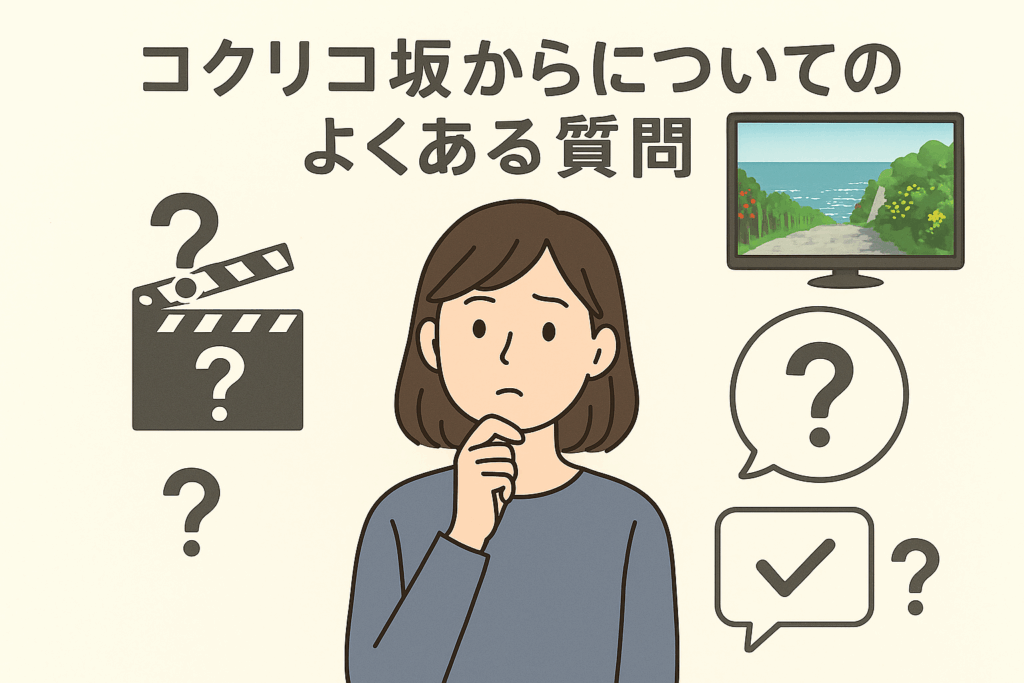
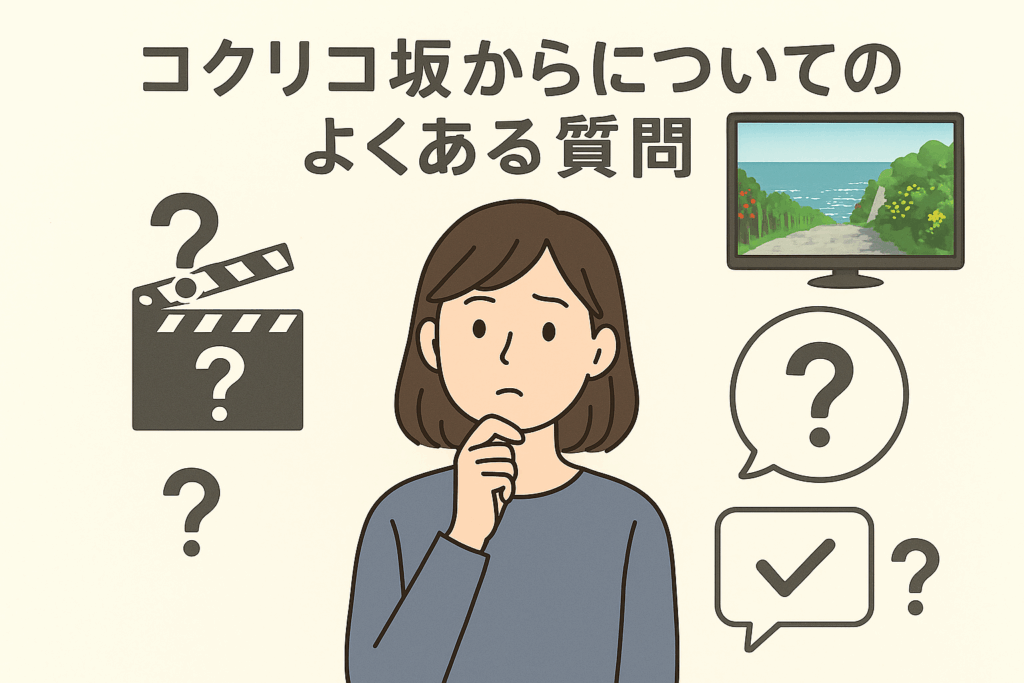
『コクリコ坂から』を観た後、多くの人が抱く疑問についてお答えします。物語の元になった話はあるのか、主人公たちの関係はどうなったのか、そしてなぜこれほどまでに評価が分かれるのか。これらの疑問を解消することで、作品への理解がさらに深まるはずです。
『コクリコ坂から』は実話を基にした作品?
結論から言うと、『コクリコ坂から』は特定の実話に基づく物語ではありません。この物語は、1980年に雑誌「なかよし」で連載された高橋千鶴さんと佐山哲郎さんによる少女漫画が原作です。
ただし、物語の背景となっている1963年という時代設定や、主人公の父親が朝鮮戦争時の機雷掃海活動中にLST(戦車揚陸艦)の事故で亡くなったというエピソードには、史実が反映されています。 このように、フィクションでありながらも、歴史的な事実を背景にしている点が、物語にリアリティを与えています。
結局、主人公たちは兄弟関係だった?
物語の終盤で、主人公の海と俊には血の繋がりがないことがはっきりと証明されます。 物語の途中で二人は同じ「澤村雄一郎」という人物の子供ではないかという疑惑が持ち上がりますが、これは誤解でした。俊の本当の父親は、澤村雄一郎の戦友であった「立花洋」という人物です。
戦後の混乱の中で立花夫妻が相次いで亡くなり、その子供であった俊を澤村が引き取って自身の戸籍に入れ、その後、現在の養父母である風間家に預けられた、というのが真相です。 したがって、二人は兄妹ではなく、恋愛し結婚することにも何ら問題はありません。
『コクリコ坂から』が評価が分かれるのはなぜ?
本作の評価が分かれる最大の理由は、そのテーマと作風にあります。まず、兄妹かもしれないという設定が、一部の視聴者にとっては受け入れがたいものでした。また、ファンタジー要素がなく、学生たちの活動や出生の秘密といった現実的なストーリーが「ジブリ作品に期待するものと違った」と感じる人もいます。
さらに、1963年という時代背景への知識や共感度によっても、作品の受け取られ方が大きく変わってきます。 このように、視聴者がジブリ作品に何を期待するか、そして物語のデリケートなテーマをどう捉えるかによって、賛否がはっきりと分かれる作品だと言えるでしょう。



やはり、二人が本当に兄妹なのかどうかが一番気になるところですよね。物語の結末を知ると、それまでのモヤモヤも少しスッキリするかもしれません。
コクリコ坂からが賛否両論ある理由まとめ
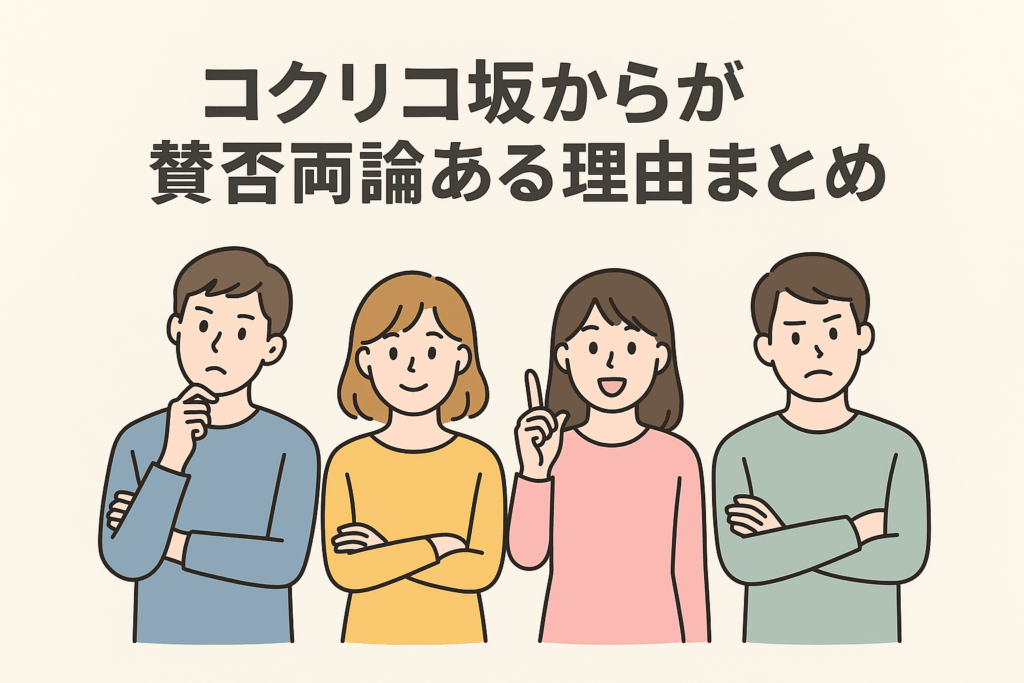
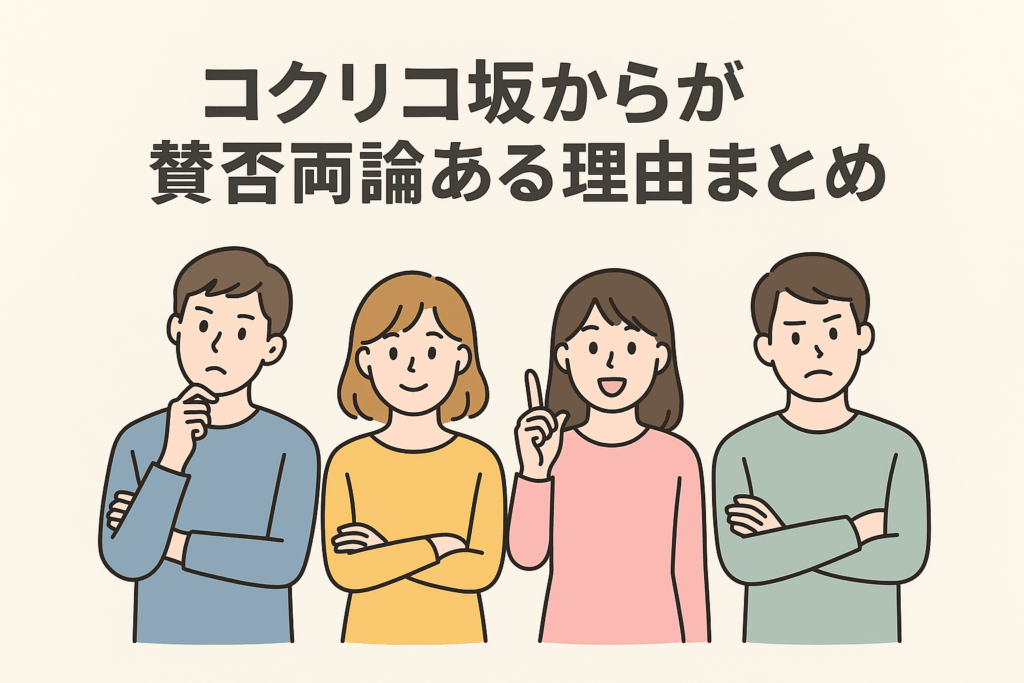
『コクリコ坂から』について、一部で否定的な意見が見られる理由から、その魅力、そしてよくある質問までを解説してきました。兄妹かもしれないという設定や、ファンタジー要素のない現実的なストーリー展開が、一部の視聴者には受け入れがたい側面があるのは事実です。
しかしその一方で、映画オリジナルの舞台である「カルチェラタン」の魅力、丁寧に描かれた昭和レトロな世界観、そして逆境の中で育まれる純粋な恋愛模様は、多くのファンを惹きつけてやみません。この作品は、観る人の価値観や時代背景への理解度によって、評価が大きく変わる、非常に繊細なバランスの上に成り立っています。 この記事を通して、あなたが抱いていた疑問が少しでも晴れ、作品を多角的に見るきっかけとなれば幸いです。



このように、見る人の視点によってガラッと印象が変わるのが『コクリコ坂から』の面白いところです。この記事を参考に、ぜひもう一度作品を見返してみてくださいね。